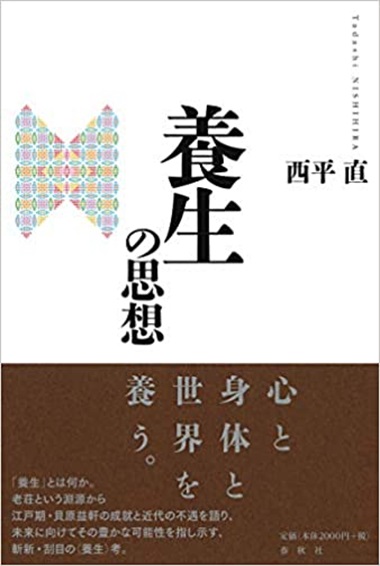養生ということ
石井智恵美
オミクロン株によるコロナ感染が増えて、対面礼拝がまたしても休止となり、そこで「まど」も再開することになりました。
先日、知り合いの方からオンラインの読書会の案内があり、参加しました。そのテーマが「養生の思想」だったのです。その本を執筆された西平直先生(京都大学教育学部・教育哲学)と、若手研究者との対話で読書会は進行しました。西平先生とは、20年前、私が富坂キリスト教センターの研究主事をしていた時に、同じ研究会でご一緒して以来のご縁でした。『現代世界における霊性と倫理』(行路社、2005)という本に研究の成果をまとめましたので、関心のある方はどうぞご覧ください。その後西平先生は『世阿弥の稽古哲学』、『稽古の思想』、『修養の思想』などをまとめられ、今回『養生の思想』をまとめられました。一環して自己形成の諸実践をテーマにしておられます。
皆さんは、「養生」というと何をイメージされますか?「養生してください」という言葉は、手術や大病をした人にかける挨拶の言葉をして日常生活に定着しています。「自分をいたわる」「心身の調子を調える」などの意味で使われることが多い言葉です。コロナ禍の今、わたしたちが「養生」ということを考えてゆくことは大切なことだ、この読書会に参加してあらためて思いました。
皆さん、それぞれ養生の方法があるのではないでしょうか。「ぬるめのお風呂に長く入る」とか「野菜ジュースを欠かさない」とかいろいろの養生法を、きっと一人一人がお持ちではないでしょうか。「養生」はその意味で、とても個性的でこれ、という正解はないものです。一人一人の工夫が大切であるというところがとても面白い、と思います。
西平先生は、貝原益軒という江戸時代の元禄時代に活躍した儒学者の「養生訓」から養生の思想をまず、紹介してくれました。養生とは、気(生命エネルギー)を養うことで、その際、気の循環を大切に考えます。そして、その方法として「節制」と「楽」を説いたというのです。「節制」は文字通り、欲望を制御すること。なぜ、欲望を制御するのか、内欲は気の循環を阻害するからです。それゆえ節制をすすめます。しかし、同時に「楽」を失わずに楽を実現することも勧めます。すなわち欲望を抑制するが、抑制しすぎるのもよくない、適度に満たすことが必要、その「宜しき分量」を見定めることが大切である、と説きます。その分量は人によって違うため、各自の判断に任されています。
また、興味深かったのは益軒の「信仰によらず自ら対処できることに目を向ける」という注意点です。「養生」は、自己形成の一過程であり、宗教的な修行の一過程でもあるのですが、とても合理的な考え方である、と思いました。私たちの信仰においても、いたずらに神に頼るのではなく、自ら対処できるところに目を向けて、自分にとっての「宜しき分量」を見定める生活の態度が、心身の健康につながり、ひいては健やかな神との関りにつながるのではないか、とおもいました。今度会った時には、それぞれの養生法をぜひ、教えてください。